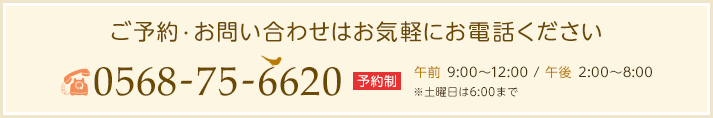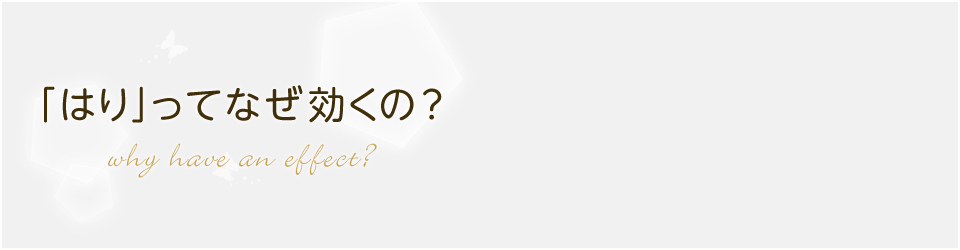
おねがい
attention
東洋医学に全く馴染みのない方を対象にまとめてみました。
専門的には多分に語弊がありますので、知識者の方はご理解をお願いいたします。
経絡治療の治療理論
経絡治療とは、全身を巡るあるいは存在する「気」の状態を整備し、「気」の流れを正常化することによって病気を治していきます。
目に見えない概念だけの医学ですので、慣れてその世界に入り込まないと理解が難しいと思います。
「気」と「陰陽」と「五行」
「気(気・血・津液)」と「五臓」には深い関係があります。
そして五臓は「陰」に属しています。詳しくは省きますが「気・血・津液」にも「陰・陽」があります。
これらが切っても切れない関係を持ち、均衡を保つことによって正常な生命活動を維持しているのです。
「経絡」と「経穴(ツボ)」
臓はその臓の気が流れる経絡に繋がっています。
各臓の経絡は順次繋がっており、全ての経絡が1本に繋がっています。
また最後が最初に連なっているので、1つの環状を成す形で全身をくまなく巡回しています。
その経絡上の重要なポイントが「経穴」です。
例えるならば「経絡は線路」「経穴が駅」といったところでしょうか?
「気・血・津液」の変動は「経絡」「経穴」に反応を現わします。
「経絡・経穴(ツボ)」と「気」
経絡に従って、気が流れると理解してください。
経穴は気の変動が現れやすいところなのです。
なぜ「はり」が効くのか?
経絡治療家はその独特の診断技術により、現れている症状の何臓の気(気・血・津液)が、どのように変動しているかを判断します。
そしてその変動が現れている「経絡」「経穴(ツボ)」を選び、その刺鍼技術をもって変動を修正するのです。
結果、気の流れが整えられることにより、出現している症状を緩和させ治癒に導くのです。